こんにちはHANAです。
誰もが一度は口ずさんだことのあるご当地ソング。
昭和の時代、日本は高度経済成長を遂げ、都市部への人口集中が進みました。
そんな中、故郷を懐かしむ人々に向けて、数多くの「ご当地ソング」が生まれました。
これらの歌は、その土地の風景や文化、人々の暮らしを情感豊かに表現し、聴く人の心に温かい郷愁を呼び起こします。
今回は、昭和歌謡を彩るご当地ソングの魅力について、時代背景や文化、旅、個人的な思い出、音楽的分析など、様々な角度から深掘りしていきます。
ご当地ソング「戦後の昭和歌謡」は望郷と希望を与えてくれた
昭和は、日本の社会が大きく変化した時代でした。
戦後の復興から高度経済成長へと向かう中で、人々は都市部に移り住み、故郷を離れることが多くなりました。
そんな時代背景の中、ご当地ソングは、故郷を懐かしむ人々の心を癒す存在として、大きな役割を果たしました。
美空ひばりさんの「リンゴ追分」(1952年)は、戦後の復興期に、望郷の念を抱かせる歌として広く愛された1曲です。
弘前市には「リンゴ追分」の歌碑が建立されています。
2024年の連続テレビ小説『ブギウギ』で若い人たちへも知れ渡った
笠置シヅ子さんの「東京ブギウギ」( 1947年)は戦後の日本に元気を取り戻せてくれました。
2025年は原爆投下からちょうど80年経ちます。
藤山一郎さんが1949年に歌った「長崎の鐘」
この曲は、当時の日本社会に深く共鳴し、多くの人々に希望と勇気を与えました。
歌詞には原爆の悲惨さを直接的に描写する言葉はなく、戦災で傷ついた人々への鎮魂歌として、そして復興への願いを込めた歌として、広く受け入れられました。
今年の夏は原爆投下から80年、改めて平和への願いを強く訴えたいですね。
ご当地ソング昭和歌謡、演歌は北国の曲や「女(ひと)」がつく楽曲が多かった
私は60代なので、昭和のご当地ソングの演歌と言えば、何度も芸名を改名し、「五木ひろし」で1971年再デビューし「よこはま・たそがれ」が、オリコン1位を獲得し複数の音楽賞を受賞しましたので、こちらが真っ先に思い浮かびます、マイクを左手で持ち、右手は拳を握って動かしながら歌う姿が印象的でした。
また、演歌のご当地ソングと言えば、やはり北国の荒涼とした風景と、故郷を思う切ない心情を重ね合わせ、多くの人々の心を捉えます。
ご当地ソング昭和歌謡、北国を舞台にした5選
北国の春/千昌夫:1977年
故郷への切ない思いを歌った、世代を超えて愛される名曲。
雪解けを待ちわびる北国の情景が、目に浮かぶようです。
一度聴いたら忘れられない、哀愁漂うメロディーが魅力です。
襟裳岬/森進一:1974年
フォークソングが全盛期で、吉田拓郎さんが作曲した楽曲を演歌の森進一さんが歌うとなり話題となりました。
演歌とフォークの連携は、その後の歌謡界に大きな影響を与えた1曲でした。
津軽海峡冬景色/石川さゆり:1977年
ご当地ソングの女王(「天城越え 」などもあります)、石川さゆりさんの代表曲。
津軽海峡の荒涼とした冬景色と、切ない女心を歌い上げた名曲です。
歌詞に登場する「上野発の夜行列車」は、今や廃止となってしまいましたが、この曲を聴くと、当時の旅情が蘇ります。
みちのくひとり旅 / 山本譲二: 1980年
最愛の女性との別れを決意した男の葛藤と、未練を抱えながらも一人旅に出る姿を描いた歌です。
歌詞には具体的な地名(松島・白河)が登場するものの、情景描写は少なく、男の心情に焦点が当てられています。
雪國(ゆきぐに)/吉幾三:1986年
雪煙をあげて走る奥羽本線の列車の姿を観て「女の人が男の人を追う詞にしよう」と歌詞を思いついたそうです。
ご当地ソング「女(ひと)シリーズ」と呼ばれて全国各地を歌っていた演歌の大御所とは?
演歌の大御所「北島三郎さん(サブちゃん)」が日本各地をテーマに恋模様を唄った楽曲は、通称「女(ひと)シリーズ」と呼ばれておりました。
調べてみると、北は北海道から南は沖縄まで、こんなに沢山のご当地ソングをサブちゃん(北島三郎さん)は歌っていたとは…私も初めて知りました。
| 函館の女 | なごやの女 |
| 尾道の女 | 沖縄の女 |
| 博多の女 | 木曽の女 |
| 薩摩の女 | みちのくの女 |
| 伊予の女 | 横浜の女 |
| 伊勢の女 | 箱根のおんな |
| 加賀の女 | あじさい情話 |
| 伊豆の女 | 千代田の女よ |
みなさんの故郷やお住いの歌もサブちゃんは歌っているかな?
「女」がつく楽曲はサブちゃんだけでなく、いろんな方が歌っていましたが、あの宇多田ヒカルさんのお母さんである藤圭子(ふじけいこ)さんもその一人、「新宿の女」を1969年に発売しておりました。
こちらは「女」を「ひと」と読まないで「おんな」でした。
ご当地ソングを唄った昭和歌謡のグルーと言えば、このグループでしょ!
内山田洋とクール・ファイブ
メンバーはギターの内山田洋さん、ボーカルの前川清さん、キーボードの宮本悦朗さん、ベースの小林正樹さん、サックス・フルートの岩城茂美さん、ドラムの森本繁さんという構成でした。
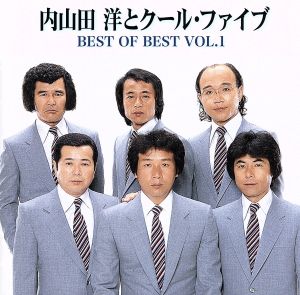
ブックオフオンラインより
観光地である長崎で飴が降るとつい皆、口ずさむのが
クールファイブがメジャーデビューした時の曲「長崎は今日も雨だった」(1969年)
内山田 洋 と クール・ファイブの楽曲には他にも数々ありますが、私の記憶に残っているのはこの3曲が印象的です。
そして、神戸(1972年)
中の島ブルース(1975年)
東京砂漠(1976年)
前川清さんの高音部分の伸びやかさは圧巻で、他のメンバーのコーラスが重なり、独特のハーモニーを生み出しています。
ムード歌謡ならではの、哀愁漂うメロディーとサビ部分の印象的なメロディーは、一度聴いたら忘れられません。
ご当地ソング昭和歌謡、ポップスでの70年代のヒット曲
ご当地ソングは海外アーテストにも
日本でも「エレキブーム」を牽引し、多くのギタリストに影響を与えた
1959年にアメリカで結成されたインストゥルメンタル・ロックバンド【ザ・ベンチャーズ】

Wikipediaより引用
左からボブ・ボーグル、ノーキー・エドワーズ、メル・テイラー、ドン・ウィルソン(1967年)
ザ・ベンチャーズは1960年代にもご当地ソングは発表しており
1966年には、和泉雅子さん・山内賢さんがデュエットした「二人の銀座」(作詞は永六輔さん)
1967年には、奥村チヨさんの「北国の青い空 」などヒット曲の作曲をしていました。
1970年代になると更に、様々なアーティストに曲を提供しました。
その中には、やはりご当地ソングもありました。
1970年「京都の恋」「京都シリーズ」第2弾として1971年に「京都慕情」を発表しました。
1971年には「長崎慕情」 この3曲は渚ゆう子さんがカバーしてシングルとして発売しヒットしました。
1971年に欧陽菲菲さんがリリースした「雨の御堂筋」は今でもカラオケで人気の1曲になっています。
ご当地ソングは、フォーク界やニューミュージックやアイドルも歌っていた
| 1971年 | 知床旅情 | 加藤登紀子 | 1965年森繁久彌リリースした曲をカバー |
| 1972年 | 瀬戸の花嫁 | 小柳ルミ子 | 瀬戸内海の美しい島々の光景が目に浮かびます |
| 1973年 | 神田川 | かぐや姫 | 3畳ひと間の下宿はもうないですね |
| 1976年 | 中央フリーウェイ | 荒井由実 | 東京競馬場とサントリー工場、よく通ります。 |
| 1976年 | 宗谷岬 | ダ・カーポ | 北海道へ行きたくなります! |
| 1976年 | 横須賀ストーリー | 山口百恵 | 同年齢の百恵ちゃん♪この歌に誘われ横須賀へ行きましたよ! |
| 1976年 | 大阪ラプソディ | 海原千里・万里 | 実姉妹のコンビ。千里さんが現在の上沼恵美子さんです。 |
| 1978年 | 東京ららばい | 中原理恵 | “トレンド・シティ” の東京のハシリの歌 |
| 1979年 | 大阪で生まれた女 | BORO | 大阪出身歌手の大阪ソング |
この他にも、60年~70年代にかけて湘南の海を舞台にした活躍した『加山雄三さん』の名曲や、70年代後半にデビューし80年代に入ると同じく湘南(茅ヶ崎)を更に有名にした、今では国民的ロックバンド『サザンオールスターズ』の数々の名曲があります。
ご当地ソングと私
私にとって、ご当地ソングは、個人的な思い出と深く結びついています。
例えば、父が好きだった「函館の女」は、父との想い出の曲になりました。
意外なことに歌唱力の高かった父、サブちゃんの歌は特に好きでどんな時でも口ずさんでおりました。
また私は幼い頃、父の仕事の関係で四国から北陸へと引越したので、「瀬戸の花嫁」では瀬戸内海の美しい風景が恋しくなったり、「北国の春」では雪国での春を待つ気持ちが懐かしくなったりと想い出を呼び起こしておりました。
ご当地ソングは、私にとって、単なる音楽ではなく、大切な思い出や感情と結びついた、特別な存在なのです。
まとめ
昭和歌謡のご当地ソングは、時代を彩り、人々の心を癒し、故郷への想いを深める、特別な存在です。
それは、その土地の文化や歴史、人々の感情を表現し、聴く人に共感と感動を与えます。
ご当地ソングを聴きながら旅をすると、その土地の魅力をより深く感じることができます。
また、ご当地ソングは、個人的な思い出と結びついていることもあります。
ご当地ソングは、音楽としても高いクオリティを持ち、聴く人を魅了する力を持っています。
ぜひ、あなたも昭和歌謡のご当地ソングを聴いて、その魅力に触れてみてください。
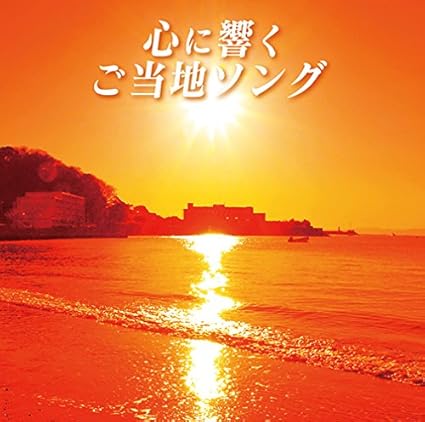


コメント